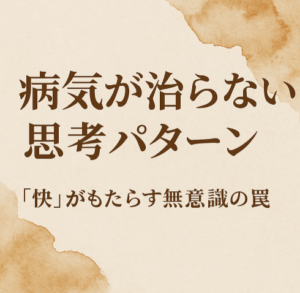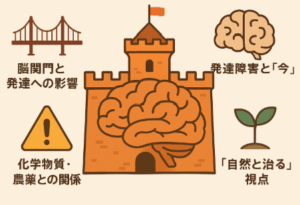違いはギフト
発達障害と「みんなと違う」ということ ~違いを怖れずに見る視点~
最近、「発達障害」という言葉を耳にする機会が増えてきました。学校や子育ての現場だけでなく、テレビやネットでも頻繁に取り上げられています。けれど、そもそも「発達障害」という言葉が使われ始めたのは、そんなに古い話ではありません。
実はこの言葉が広く認知されるようになったのは2000年代以降のことで、2005年に施行された「発達障害者支援法」によって、一気に社会的な認知が進みました。
けれど本当に、それは「新しく現れた」ものなのでしょうか?
昔から「そういう子」はいた
「発達障害」という名前がついたことで、あたかも“病気”のように見えてしまいますが、実は昔から人間社会には一定の割合で、こうした「みんなとちょっと違う」感性や行動を持つ人たちが存在していました。
むしろ、大人たちが扱いやすくするために「名前」をつけた、という側面すらあります。
社会が整然と動くためには“普通”が必要。でも、みんなが同じ方向ばかりを向いていたら、大きな災害や変化の時に社会は簡単に崩れてしまうでしょう。多様性とは、生存戦略でもあるのです。
ディスレクシア(読み書き障害)というギフト
たとえば、ディスレクシアという特性を持つ人たちは、文字の読み書きに困難を抱えることがあります。しかしその一方で、視覚的・空間的な認識に優れていたり、独特な創造性を持っていたりすることが多いのです。
有名なところでは、映画監督のスティーブン・スピルバーグや俳優のトム・クルーズもディスレクシアを公表しています。日本では片岡鶴太郎さんも知られています。
彼らは、古代であれば「シャーマン」と呼ばれた存在かもしれません。卑弥呼のように、常識の枠を超えた感覚で人と世界をつなぐ存在です。
「正しさ」や「常識」って誰が決めるのか
私たちは、「常識」や「正しさ」を、多くの人が言っていること、先生や権威ある人が言っていることに委ねがちです。
でもそれは、ただの“多数決”にすぎません。大多数の人が正しいと感じることを、無意識のうちに「善」として取り込んでしまう。これこそが、脳に入り込む“暗示”のようなものです。
子どもの心に忍び込む「正義」
たとえば、ある子どもが友達に悪口を言われたとします。ところが、その言葉の意味が分からなければ、本人は何も気にしません。
しかしそこに大人が入って、「そんなことを言っちゃダメ」と叱ったり、庇ったりした場合、どうなるでしょうか。
子どもはこう思うかもしれません。
「大人が怒ったということは、自分ってやっぱり“変”なのかな…」
つまり、大人の“正義”が、かえって無意識に「あなたはおかしい」と伝えてしまうこともあるのです。
暗示は無意識に根を張る
こうした小さな体験が、子どもたちの無意識に積み重なっていきます。
それはやがて、自分を他人と比べる物差しになり、「どうせ自分は…」という思考の癖を作ってしまうのです。
だからこそ、私たち大人が今、意識したいことがあります。
「違い」は、弱点ではなく可能性の種。
「みんなと違う」は、劣っていることではなく、新しい視点を持っていること。
そんな目で、子どもたちを見守っていけたら――
未来はもっと、豊かでやさしいものになるかもしれません。
このブログは、みんな天才化機構 のBUM(*1)を振り返ったアウトプットとなります。
(*1)平日 am6:30から行われる30分のお話会
(一社)みんな天才化機構の許可を得て掲載しています。