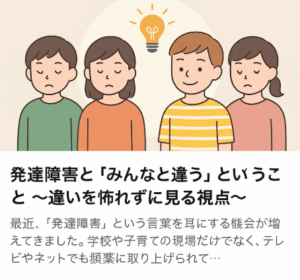病気が治らない思考パターン──“快”がもたらす無意識の罠」
病気がなかなか治らない理由のひとつに、「思考パターン」が大きく関わっていることをご存知でしょうか?
たとえば、病気になると仕事や学校を休めたり、周囲から気遣いや優しさを受けたり、病院で薬をもらい症状が緩和されたりします。
本来、病気は不快であるべきものですが、こういった一連の出来事が“快”と感じられてしまうことがあります。
このような「快」の経験が無意識に刷り込まれてしまうと、「病気であること=得られるメリット」として認識されるようになり、結果的に病気を繰り返してしまうのです。
これは「ノンシーボ効果(nocebo effect)」と呼ばれる現象にも関連しています。
※ノンシーボ効果:プラシーボ(偽薬)とは逆に、思い込みによって症状が悪化したり、本来起きない副作用を感じたりする心理的・身体的反応のこと。
発達障害のラベルと現代の生活環境
最近、子どもの「発達障害」という言葉をよく耳にするようになりました。
しかし、子どもとは本来「落ち着きがないもの」ではないでしょうか?
その子どもたちの行動の背景には、日々口にする食べ物や生活環境が強く影響しています。
-
添加物たっぷりのお菓子
-
化学薬品や農薬が使われた食品
-
ミネラルが不足したコンビニ弁当や加工食品
これらは身体にとって必要な栄養素を奪い、ホルモンバランスや自律神経の乱れを引き起こします。
さらに、過度なデジタル環境やネット依存によって、交感神経と副交感神経のバランスも崩れ、子どもの精神状態にまで影響が及びます。
無意識の「ラベル付け」が作る未来
そのような環境の中で、親や先生が「この子は発達障害だ」とレッテルを貼ると、子どもはそれを受け入れ、自分自身に言い聞かせてしまいます。
「自分は発達障害だから、こうなんだ」
「自分にはできない」
こうして、自分の存在や行動に対する思い込み=思考パターンが出来上がっていきます。
本当に問題なのは何か
子ども自身ではなく、
その子を取り巻く大人たちの“無自覚な思考パターン”が、子どもにそのまま受け継がれているのかもしれません。
私たちがまず変えるべきなのは、
環境と大人の思考パターンなのです。
このブログは、みんな天才化機構 のBUM(*1)を振り返ったアウトプットとなります。
(*1)平日 am6:30から行われる30分のお話会
(一社)みんな天才化機構の許可を得て掲載しています。