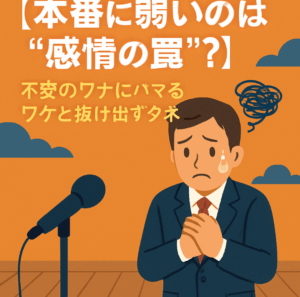「病は氣から」は本当だった!
感情と免疫力の深い関係──整える鍵は、朝の習慣と腸内環境にあった
私たちの「感情」は、思っている以上に「免疫力」と密接に関わっています。病は“氣”からと言われますが、その“氣”は「心」、そして「心」は食事や生活習慣、環境からつくられています。
かつての昭和期の医学では、人の感情や暗示の受け取り方を重視し、病名をあえて伝えない配慮さえありました。それほどまでに、心が体に与える影響は大きいのです。
感情と脳のメカニズム
脳の「扁桃体」は恐怖や危機への感情を司り、それをコントロールするのが「前頭前野」です。ところが、睡眠不足やストレスで前頭前野の働きが落ちると、感情のブレーキが効かなくなってしまいます。
特に子どもや若年層では、前頭前野が発達途上であり、不安や怒りのコントロールが難しくなりがちです。ここに、ゲームや夜更かし、食生活の乱れが加わると、感情の不安定さが加速し、心の不調へとつながってしまいます。
血糖値と腸内環境の関係
イライラや焦燥感、思考停止の背景には「血糖値の乱高下」があります。食事を整えるだけで、学校での問題行動が減るというデータもあるほどです。
腸は単なる消化器官ではなく、ホルモン(例:セロトニン)や免疫細胞を生み出す重要な臓器です。腸内環境が悪化すると不安感が増し、心の安定にも影響します。
納豆やヨーグルトなど、単一の菌ばかりに偏るとバランスを崩すことも。理想的なのは、自分の手で仕込んだ発酵食品や、育てた野菜を摂ること。畑の土には自分の常在菌が含まれ、それが腸にも良い影響を与えるといわれています。
整えるべきは「生活リズム」
夜遅くに食事をするようになったのは、照明技術の発達によるものです。本来、人間は昼型の動物であり、太陽が昇る前に目覚め、日が沈む頃には活動を終えるのが自然なリズムです。
朝日を浴びるだけで、自律神経が整い、心もすーっと軽くなります。虫や鳥の声に耳を傾け、深呼吸して一日を始める。これが本来の私たちの姿かもしれません。
朝の想像力が感情を導く
感情を整えるには、朝がカギです。起きたら未来の自分を思い描きましょう。「こうなりたい」「今日やり遂げたいこと」をイメージすることで、前向きな感情が湧き出し、自然と行動が変わります。
また、呼吸法やヨガ、チャクラの意識など、姿勢や呼吸を整えることも、心を落ち着かせる助けになります。
—
今日からできること
– 朝日を浴びて、自律神経を整える
– 食事の内容とタイミングを見直す
– 発酵食品を自分で仕込んでみる
– 深い呼吸を意識し、心を落ち着ける
– 毎朝、未来の自分をイメージしてみる
このブログは、みんな天才化機構 のBUM(*1)を振り返ったアウトプットとなります。
(*1)平日 am6:30から行われる30分のお話会
(一社)みんな天才化機構の許可を得て掲載しています。